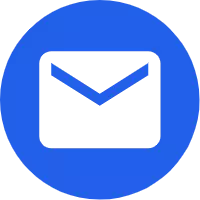戦術的な応急処置エッセンシャル - 猫の止血帯
2025-02-14
戦闘中、猫のターンスタイル広く使用されており、無数の兵士の命を救っています。
猫の止血帯通常、ナイロンストラップ、ドローストリングバックル、ベルクロ、スピニングロッド、C字型のロックバックル、その他のコンポーネントで構成されています。この猫の止血帯には大きな利点があり、操作が容易で、安定した信頼性の高い止血効果があり、持ち運びが簡単です。使用すると、肌に接触する必要はなく、衣類の袖の外側に直接結び付けることができます。これにより、使用の利便性が大幅に向上します。止血の原理は、固定後にナイロン自己接着テープを締め、完全な止血の目的を達成するためにツイストロッドを回転させて締めて締めることです。単一の回転止め止めが出血を効果的に停止しない場合、その上に別の止血帯を適用して、完全な止血を確保することができます。
猫の止血帯負傷者自身が操作できる一種の止血ツールであり、血液が流出するまでストラップの連続的な締め付けを通じて、強さは自分自身によって制御され、止血帯は身体の固定部分で操作プロセスを完了するまで腰を下ろします。
止血帯の詳細な使用:
(1)止血帯を塗る前に、負傷した肢を上げて、静脈血の中心性回復を増加させ、血流を遅くする必要があります。
(2)止血帯をすばやく取り外し、接着テープを開き、止みの傷から約5センチメートルの四肢の近位端に止まり、自己接着テープをしっかりと引っ張り、接着を覆します。回転棒を回して、傷に出血の兆候がなくなるか、手足の遠位端で動脈脈動を感じないようにします。次に、スイベルバーを固定スロットにスナップし、固定留め金でスイベルバーと自己接着テープをロックします。
(3)結合部位に注意を払ってください:上肢の出血については、止血帯を上腕の中央と上3分の1に結び付ける必要があります。下肢の出血の場合、止血帯は太ももの近くに縛られるべきです。止血帯は、前腕、ふくらはぎ、肘関節、膝関節、またはピアス部分に置かれるように避けるべきです。
(4)止血帯ユーザーは、止血帯の使用の開始時間を迅速かつ正確に記録する必要があります。
猫の止血帯の使用に関する注意事項:
1。クイックアクセスの原則:必ず配置してください猫の止血帯アクセスしやすい位置にあるバックパックやその他のストレージ機器では、バックパックの底に配置することは厳密に禁止されています。戦争の出血状況に直面したとき、それはセルフヘルプの最初の選択です。出血を止める必要性を明確に示したら、その後の救助のためにゴールデンタイムを購入するために、最初にためらうことなく使用する必要があります。
2。使用の厳格な兆候:戦場のすべての人員は、極端な環境で壊れやすく、出血を効果的に止めることができないため、戦場のすべての人員に専門的に推奨されるスピニング止めを装備する必要があります。
3。衣服の干渉を避ける:止血帯を使用する場合、軍服、ユニフォームなどの衣服をひっくり返したり除去したりしないでください。出血の位置を正確に決定し、衣服の動きのために出血点の判断を妨げることを避けるために、元の状態に衣服を保管しないでください。
4。特別な状況の取り扱い:出血の場所を定義するのが難しい場合、または視力が夜間の手術中に制限されている場合、または犠牲者が複数の負傷を負う複雑な状況がある場合、止血帯の使用は「高くてタイト」の原則に従う必要があります。
5.マルチテープの使用規範:最初の止血帯が出血を止めることができない場合、心臓の近位(上)端に2番目の止血帯をすばやく追加する必要があります。止血効果に影響を与えないように、2つの止血帯の縛られた棒が互いに干渉しないようにするために特別な注意を払う必要があります。
6。関節の禁忌:止血帯を縛るときは、膝または肘の関節を渡らないようにします。これらの関節の特別な解剖学的構造のため、ここにある止血帯は止血の効果が不十分になり、出血を効果的に止めることはできません。
7.犠牲者の状態の監視:止血帯を適用した後、止血症の圧力が十分に緊密であり、出血が効果的に制御され、異常が見つかったらタイムリーな調整を行うことを保証するために、死傷者の生命徴候と出血状態を綿密に監視する必要があります。
8。繰り返しの評価要件:止血帯を適用した後、繰り返し評価の認識を確立する必要があります。止血の影響、負傷した四肢の状態などを途切れることなく、止血帯の使用を迅速に調整するか、評価結果に従って他の必要な治療措置を講じます。
猫の止血帯操作が簡単で、出血を止めるのに迅速かつ効果的であり、戦場で兵士のお気に入りになりました!従来のガーゼ止血包帯と比較して、2つの特性があります。まず、高速であり、数秒で止血効果を達成できます。第二に、それは一人の兵士によって運営されることができます。同志や医者の助けがなければ、自分自身の出血をすぐに止めることもできます。